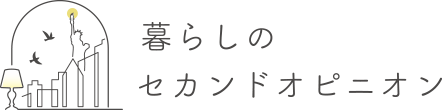【徹底解説】自動車保険の無駄を見直す 特約の知識

自動車保険は、車を運転する上で必須とも言える保険ですが、その正しい入り方を知っている人は少ないかもしれません。
運転時に起きた事故に対して、保険という手段だけで解決しようとせず、「社会保険からどのようなお金が出るのか」も含めて検討する必要があります。
自動車保険は、多くの方が年間1万円から5万円もの保険料を余計に支払っている可能性があり、適切な見直しによって大幅な節約が期待できます。
この記事では、多くの人が陥りがちな自動車保険の「よくわからない特約」を深堀り、最適な自動車保険の選び方と見直し方を解説します。
最初に申し上げますが、感情はなるべく切り離して考えることが大切です。
もちろんあるに越したことはないのは、全ての商品において言えることですが、「手段は保険だけではない」ということを念頭に置き、冷静に判断できるようになりましょう。
自動車保険の基本と加入の重要性
自動車保険は、万が一の事故が起こった際に、自身の力では対応できないような巨額なリスクに備えるためのものです。
車に少し傷がついたといった軽微なリスクではなく、人を死傷させてしまったり、多額の物を壊してしまったりといった、人生を左右しかねない大きな損害に備えることが保険本来の目的という前提条件を抑えておきましょう。
車を購入すると、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務付けられています。これは車検を通す上でも必須であり、公道を走る車は基本的に全て加入しています。
しかし、自賠責保険が補償するのは対人事故による損害賠償のみであり、その補償額も死亡で最高3000万円、後遺障害で最高4000万円、傷害で最高120万円と、決して十分ではありません。
たとえば、お医者さんのような高収入の属性の方を死傷させてしまった場合、5億円以上の判決が出たケースもあります。
そのため、自賠責保険では足りない補償を補うために、任意の自動車保険への加入が必要となります。
必要不可欠な補償内容
任意の自動車保険で最も重要なのは、以下の2つです。
- 対人賠償保険の無制限
運転中に人を死傷させてしまった場合の損害賠償を補償するものです。交通事故による高額賠償判決では、5億円を超える損害賠償請求が認められたケースもあります。特に、医師や将来有望な若者などが事故により死亡したり、重い後遺症が残ったりした場合には、数億円規模の賠償請求が当たり前となることもあります。そのため、補償額には上限を設けず、「無制限」に設定することが極めて重要です。
- 対物賠償保険の無制限
他人の財物に損害を与えてしまい、損害賠償を請求された場合の保険です。電信柱への衝突による修理費用だけでなく、それによって周囲の電力が止まり、広範囲から損害賠償請求されるといった間接的な損害も発生する可能性があります。また、店舗に突っ込んで営業ができなくなった場合、直接的な修理費用だけでなく、店舗が運ぶ予定だったものの輸送不能による営業損失など、間接的な損害も含まれて算定されます。物の価格には限りがあると思われがちですが、間接損害を含めると数千万円規模の請求となる可能性もあるため、こちらも補償額は「無制限」に設定することが推奨されます。
これら対人・対物賠償の無制限こそが、自動車保険の根幹であり、最低限備えるべき補償だと言えます。
保険料を決める詳細な条件と最適化
自動車保険の保険料は、様々な条件によって大きく変動します。これらの条件を適切に設定することで、保険料を効果的に抑えることができます。
1.ノンフリート等級
- 自動車保険には「ノンフリート等級」という割引制度があり、自動車が9台以下の場合に適用されます。等級が高いほど事故を起こす確率が低いとみなされ、保険料が安くなります。
- 通常、新規契約は6等級からスタートし、1年間無事故で過ごすと1等級ずつ上がります。しかし、保険を使用する事故を起こすと、3等級ダウンしてしまいます。
- 2台目以降の車を契約する際には、「セカンドカー割引」によって7等級からスタートできるケースもあります。
- 3年契約などの長期契約も可能ですが、途中で車に乗るのをやめたり、乗り換えたりした場合は途中解約ができ、未利用期間の保険料は戻ってきます。ただし、この長期契約は、割高な店舗型の大手損保に限られることが多く、ネット型のダイレクト損保では基本的に1年更新が前提となります。効率的で安い保険を選ぶには、1年ごとの更新が推奨されます。事故を起こす可能性が高い免許取り立ての方は3年契約を考えてもよいと思います。
2.運転者の範囲の限定
- 保険の対象となる運転者を限定することで、保険料を抑えることができます。
- 本人限定:本人のみ運転
- 本人・配偶者限定:本人と配偶者のみ運転
- 家族限定:本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が運転
- 限定なし:誰が運転しても補償
- 下に行くほど(限定しないほど)保険料は高くなります。家族以外が運転する機会が少ない場合は、不必要に範囲を広げないことが重要です。
3.運転者の年齢条件
- 自動車事故の発生率は10代が最も高く、年齢が上がるにつれて減少しますが、60歳を超えると身体能力の低下により再び事故率が上がると言われています。
- 保険会社によって区分は異なりますが、一般的には「全年齢補償」「21歳以上」「26歳以上」「30歳以上」「35歳以上」などで区切られます。年齢条件を高くするほど保険料は安くなります。
- 重要な点として、この年齢条件は同居する家族のうち、自動車を運転する人の最も若い年齢を基準に設定します。
もし、運転者限定条件を「限定なし」に設定し、家族の年齢条件を「30歳以上」に設定している場合でも、25歳の会社の後輩が運転して事故を起こした際には、しっかりと補償が適用されます。
家族以外で若い人が運転する可能性があるからといって、無駄に「全年齢補償」にする必要はありません。
- 誕生日を迎えて年齢条件が変わる場合(例:29歳から30歳になった時など)は、すぐに保険会社に連絡することで、日割り計算で保険料が安くなり、差額が返還されることがあります。
4.車の形式(年式、車種、排気量など)
車の年式、軽自動車か大型車か、自動運転サポートの有無、排気量、車種によって保険料は異なります。安全性能が高い車ほど保険料は安くなる傾向にあります。
5.免許証の色
免許証の色は「ゴールド」「ブルー」「グリーン」の3種類があり、無事故無違反の「ゴールド免許」が最も保険料が安くなります。
6.想定走行距離
- 年間の走行距離に応じて保険料は変わります。走行距離が短ければ保険料は安くなりますが、保険料を安くするために虚偽の申請をすると、告知義務違反となり、最悪の場合、保険金が支払われなかったり、強制解約されたりする可能性があるため注意が必要です。
- もし、途中で実際の走行距離が当初の申請を超えそうな場合は、早めに保険会社に連絡することが推奨されます。
7.自動車の使用目的
- 自動車の使用目的は、保険料に大きく影響します。主に「業務使用」「通勤・通学使用」「日常・レジャー使用」の3つに分けられます。保険料は「業務使用」が最も高く、「日常・レジャー使用」が最も安くなります。
- 月平均15日以上の利用があるかどうかが区分の目安です。
- 幼稚園の送迎:学校教育法上の「学校」に該当するため、月15日以上の送迎があれば「通勤・通学使用」となります。
- 保育園の送迎:学校扱いではないため、毎日送迎していても「日常・レジャー使用」で問題ありません。
- 駅までの送迎:直接会社や学校に行っていないため、「日常・レジャー使用」に該当します。
- アルバイトやパートの通勤:月15日未満の利用であれば、「日常・レジャー使用」に該当します。
- 「たまに通勤で使うから」と安易に「通勤・通学使用」を選んでいる人が非常に多いですが、実際には「日常・レジャー使用」で済むケースが多いため、自身の車の使い方を再確認し、見直すことが重要です。
契約途中でも使用目的の変更は可能で、差額の保険料が返還されます。
不要または慎重に検討すべき特約
多くの人が不必要に高い保険料を支払っている原因の一つに、不要な特約への加入があります。
1.対物超過特約
相手の車の修理費用が時価額を超えた場合に、その超過分を補償する特約です。ただし、多くの場合、補償上限額が50万円などと設定されており、人生が破綻するような大きなリスクには備えられていません。レアケースであり、補償額も限定的であるため、基本的には不要だと考えられます。
2.人身傷害保険(重要)
- 「自動車に乗っている人」が事故により怪我をしたり死亡したりした場合に、治療費などの実損害額を補償するものです。医療保険と重複する部分が多く、日本の高額療養費制度や医療費3割負担の仕組みを考えると、民間の医療保険と同様に、基本的に不要と考えてよいです。もちろん、生活防衛資金が貯まっていない家庭では負担になってきますので、ご自身の家計状況によってご判断ください。どちらにせよ、優先度は高くない特約になります。
- 他人に過失がある事故の場合、相手方の保険から賠償が支払われます。自分に過失がある事故の場合でも、「医療費の自己負担分」を支払えば済む話であり、わざわざこの特約で備える必要性は低いでしょう。また、同乗者が死傷した場合でも、最初に述べた「対人賠償保険の無制限」で補償されるため、人身傷害保険と重複します。
- ネット型のダイレクト損保の中には、この特約が自動付帯で外せないケースもありますが、その場合でも費用負担は比較的小さい(年間数千円程度)ため、諦めて付帯させるか、外せる保険会社を選ぶのが良いでしょう。
3.搭乗者傷害保険
- 人身傷害保険と似ていますが、こちらは事故により定額の保険金が支払われるものです。人身傷害保険が実費を精算するのに対し、搭乗者傷害保険は入院日数や手術内容などに応じてあらかじめ定められた金額が支払われる点が異なります。
- こちらも人身傷害保険と同様に、日本の医療保険制度や高額療養費制度、そして「対人賠償保険の無制限」の補償範囲と重複するため、基本的に不要と考えられます。
友人や家族を乗せることが多いからといって必要性を感じるかもしれませんが、対人賠償無制限に加入していれば、同乗者への補償はすでにカバーされています。
4.車両保険(重要)
- 車両保険は、保険料を高くしている最大の要因です。自身の車の損害を補償するもので、既に加入している場合は解約することで保険料を大幅に削減できます。解約すれば月割りで保険料が返還されます。
- 車両保険は、対物超過特約と同様に、時価額を上限としてしか支払われません。新車で購入したとしても、時間が経つにつれて車の価値は下がるため、たとえ全損しても新車が買えるだけの金額が戻ってくるわけではありません。
- また、擦ったりへこんだりといった軽微な事故の場合、板金修理などで数万円から数十万円で済むことが多く、多くのケースで10万円までの「免責金額」が設定されています。これは、修理費用が10万円以下なら自己負担、10万円を超えた部分のみ保険金が支払われるということです。結局、自己負担が発生する上、保険を使用すると等級が下がり、翌年度の保険料が上がってしまうため、結果的に持ち出しの金額が大きくなりがちです。
- 万が一、自分の過失で車を全損させるような事故を起こす場合は、そもそも車の運転そのものを控えるべきレベルのリスクです。軽微な損傷であれば実費で直せばよく、高額な修理費用がかかる場合は、その車を修理せずに安い中古車に乗り換えるという選択肢もあります。他人の過失による事故で全損した場合は、相手側の保険で対応されるため、車両保険の必要性は低いと言えます。
※前提として、運転技術が未熟な時期や貯蓄が少ない家庭であるのに高級な車を買うということはリスクが高いということです。もしそれでも欲しい車に乗りたいのであれば、そのリスクや車両保険料も含めて支払能力があるかまで考えて自動車は購入しましょう。
- 車両保険を外すだけで、年間3万円から5万円ほど保険料が安くなることは珍しくありません。この浮いたお金を貯蓄に回したり、車の維持費以外の支出に備えたりする方が、資産形成という観点からも合理的です。保険の「万が一の大きなリスクに備える」という本質から考えると、車両保険はなくてもよい特約だと言えます。
5.弁護士費用特約
- 事故に遭った際に、弁護士にかかる費用を補償してくれるものです。この特約は、自分が加害者ではなく、被害者になった時に役立ちます。
- 自分が加害者になった場合、保険会社が相手方との示談交渉を代行してくれるため、基本的に自分で弁護士を雇う必要はありません。
- 一方、自分が被害者となり、相手に対して損害賠償請求を行う際に弁護士を雇う場合に、その費用をこの特約がカバーしてくれます。例えば、後方から追突されて骨折し、弁護士を雇って慰謝料300万円を得た場合、成功報酬として弁護士に支払う約72万円などを特約が補填してくれます。
- 弁護士費用特約には「自動車事故型」と「日常生活も含む型」の2種類があります。後者は、自動車事故だけでなく、自転車事故や水漏れ被害、犬に噛まれたなどの日常生活におけるトラブルで損害賠償請求を行う際の弁護士費用もカバーします。
この特約を使用しても、保険の等級は下がりません。費用は年間0円の場合から4000円程度までありますが、高額な特約ではないため、「あっても良い」程度の位置づけです。
適切な保険会社の選び方
自動車保険を提供する会社は、大きく分けて大手損害保険会社(東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保、三井住友海上、損害保険ジャパンなど)と、ネット系のダイレクト損保(チューリッヒ、アクサ、SBI損保、三井ダイレクト、ソニー損保、イーデザイン損保、大人から自動車保険など)があります。
一般的には、ネット系のダイレクト損保を選ぶことが大前提となります。なぜなら、店舗を持たない分、大手損保と比較して保険料が格段に安い傾向にあるからです。事故対応の質についても、大手と遜色ない対応をしてくれることがほとんどです。
個々の年齢、車種、走行距離、等級などによって最適な保険会社は異なるため、「ナンバーワン」を特定することは難しいです。一括見積もりサイトも便利ですが、営業電話が多くなるデメリットもあるため、いくつかの推奨されるダイレクト損保に絞って直接見積もりを取るのが効率的です。
また、会社の団体保険が用意されている場合もありますが、大手損保が提供していることが多く、必ずしもダイレクト損保よりも安いとは限りません。年間2万円以下など非常に安い場合は見直しの必要はないかもしれませんが、比較検討する価値はあります。
これらのダイレクト損保は、ソルベンシーマージン比率(支払い能力を示す指標)が400%以上と、いずれも安定しており、支払い能力には問題ありません。電話対応についても、概ね良好な印象です。
賢い自動車保険の入り方まとめ
迷った際に抑えておくべきポイントは以下の通りです。
- 対人・対物賠償は無制限にする。
- 年齢条件、走行距離、自動車の使用目的は明確かつ正確に設定する。特に、通勤で使うことが少ないのに「通勤・通学使用」にしている場合は、「日常・レジャー使用」への見直しを検討する。
- 特約はできる限り外す。特に車両保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険は、家計管理が出来ていれば基本的に不要です。
- 弁護士費用特約は、自身の判断で「あっても良い」程度に考える。
- 保険会社は、ダイレクト損保も含め比較検討する。
これらのポイントを押さえることで、無駄な保険料を支払いすぎることなく、自分にぴったりの、そして本当に必要な補償を備えた自動車保険を選ぶことができるでしょう。保険は「万が一の際に自分の力では対応できないリスク」に備えるためのものであり、その本質を理解し、正しく活用することが重要です。
また家計管理が出来ているかどうかで、特約の必要性が変わってきます。
無駄な保険料にお金を捨てることがないように、家計管理をしっかりと行いましょう。
一人では難しい方は、30日で家計改善ができるお金のパーソナルジムがおすすめです。
どれくらい家計が変わるのか、一度お気軽にお問い合わせください。