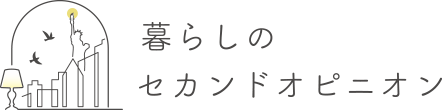【元営業が語る】住宅営業マンが本音では付けたくないオプション5選

夢のマイホーム計画、心躍るオプション選び。しかし、住宅営業マンから提案されるままに「あれもこれも」と追加していくと、予算はあっという間に膨れ上がります。
一方で、あなたが「これ、付けたいんですけど…」と相談した時、営業マンの反応がどこか歯切れ悪かったり、遠回しに他の選択肢を勧められたりした経験はありませんか?
実は、住宅営業マンには「お客様にはあまりお勧めしたくないな…」と本音では思っているオプションが存在します。それは、決して性能が悪いからではありません。コストパフォーマンス、後々のメンテナンス、そして何より「お客様に本当に満足していただけるか」という視点から、プロとしてお勧めしにくい理由があるのです。
今回は、元住宅営業マンの私が、その裏側をこっそりお話しします。なぜ彼らがそのオプションを積極的に勧めないのか?その理由を知ることで、あなたの家づくりはより本質的なものになり、無駄な出費を抑え、満足度の高い選択ができるようになるはずです。
1.浴室暖房乾燥機は「コスパが悪い」の代名詞?
一見すると、雨の日でも洗濯物が干せて、冬場のヒートショック対策にもなる「浴室暖房乾燥機」は、非常に魅力的に映ります。しかし、多くの営業マンがこれを標準仕様以上にプッシュしないのには、明確な理由があります。
なぜ勧めないのか?
驚くほど高いランニングコスト:浴室乾燥機の電気代は、意外と高額です。毎日数時間使うと、月々の電気代が数千円単位で跳ね上がることも珍しくありません。最近は省エネ性能の高いドラム式洗濯乾燥機や、除湿能力の高い除湿器があり、「わざわざ電気代の高い浴室乾燥機を使わなくても…」というのが本音です。
換気扇で十分:お風呂上がりにはスキージーで水を切り、換気扇を常に回しておけば、浴室は十分に乾燥し、カビの発生を大幅に抑制できます。つまり、カビ対策としての「乾燥機能」の重要性は、昔に比べて格段に下がっているのです。
暖房機能も出番が少ない?:最近のユニットバスは断熱性能が格段に向上しており、お湯を張るだけで浴室全体が暖かくなります。脱衣所に小型のヒーターを置くなど、より低コストで効果的なヒートショック対策も可能です。
代替案と考え方
洗濯物を乾かす目的なら、初期費用・ランニングコストともに安い「室内物干しユニット」と「除湿器+サーキュレーター」の組み合わせが最強です。リビングの邪魔にならない場所に物干しスペースを計画しておけば、天候を気にせず、経済的に洗濯物を乾かせます。
もちろん、花粉症対策で絶対に外に干したくない方や、共働きで夜間に洗濯を済ませたい方にとっては、浴室暖房乾燥機は頼れる存在です。しかし、「なんとなく便利そうだから」という理由で採用する前に、本当に自分のライフスタイルに必要か、そのランニングコストを許容できるかを一度立ち止まって考えてみることをお勧めします。
2.勝手口は「家の弱点」になりかねない
昔の日本の台所には当たり前のようにあった「勝手口」。ゴミ出しやちょっとした出入りに便利というイメージがありますが、現代の住宅においては、営業マンが設置に慎重になるオプションの代表格です。
なぜ勧めないのか?
断熱性と気密性の低下:家の中で最も熱の出入りが激しいのは「開口部(窓やドア)」です。壁に比べて断熱性能の劣る勝手口を設けることは、家の断熱性・気密性を自ら下げる行為に他なりません。夏は暑く、冬は寒い家になる原因を、わざわざ作る必要はないと考えるのがプロの視点です。
防犯上の大きなリスク: 勝手口は玄関に比べて人目につきにくく、鍵も簡素なものが多いため、空き巣の侵入経路として狙われやすい場所です。防犯性能の高いドアを選べばコストは跳ね上がり、本末転倒になりがちです。
意外とかかる設置コスト: ドア本体だけでなく、土間のコンクリート、外の照明、雨よけの庇(ひさし)、ステップ(階段)など、付帯工事で15万〜30万円以上の追加費用がかかることも珍しくありません。その割には、「使っていない」という声が多いのも事実です。
代替案と考え方
現代のライフスタイルでは、ゴミは収集日の朝に玄関から出すケースがほとんどです。「ゴミを一時的に置いておく場所」が欲しいのであれば、パントリーや土間収納の一角にスペースを設ける方が、家の性能を損なわずに目的を達成できます。もう一つおすすめなのは、「生ゴミ処理機」です。ボタン一つで乾燥ができ、生ゴミの量をかなり減らすことが可能です。補助金が活用できる地域もありますので、一度お住まいの自治体のHPを調べてみるとよいと思います。
また、庭への出入りが目的なら、リビングの「掃き出し窓」で十分です。断熱性の高い樹脂サッシの窓を選べば、家の性能を維持しつつ、勝手口以上の開放感と利便性を得られます。家庭菜園で採れた土付き野菜を運び込みたい、といった明確な目的がなければ、勝手口は「百害あって一利なし」とまでは言いませんが、慎重に検討すべきオプションです。
3.小さな窓の多用は「オシャレ」ではなく「無駄」
「デザイン性を高めるために、小さな窓をリズミカルに配置したい」 「廊下が暗いから、明かり取りに小さな窓を…」
こうした要望はよくありますが、営業マンは内心「うーん…」と思っています。小さな窓の多用は、コスト・性能・メンテナンスの全ての面でデメリットが大きいのです。
なぜ勧めないのか?
最悪のコストパフォーマンス:窓は、大きさが半分になっても価格や施工費は半分になりません。むしろ、小さな窓を複数取り付ける方が、大きな窓を一つ取り付けるよりも総額が高くなるケースがほとんどです。得られる採光や通風の効果に対して、費用が見合わないのです。
断熱性能の低下:前述の通り、窓は家の断熱上の弱点です。たとえ小さくても、その数が増えれば増えるほど、熱が逃げる箇所が増えることになります。特に目的のない小さな窓は、家の性能を下げるだけの「穴」になってしまいます。
掃除の手間と外観の乱れ:窓の数だけ、掃除の手間は増えます。また、綿密に計算されたデザインでない限り、小さな窓の乱立は外観をゴチャゴチャさせてしまい、かえって安っぽく見えてしまう危険性があります。
代替案と考え方
まず、「本当にそこに窓が必要か?」を徹底的に考えましょう。採光が目的なら、天窓(トップライト)や高窓(ハイサイドライト)を効果的に一箇所設ける方が、家全体が明るくなります。通風が目的なら、空気の通り道を計算し、効率的な位置に滑り出し窓などを配置する方が賢明です。
デザイン性を高めたいのであれば、窓の「数」ではなく、「配置」や「種類」で工夫しましょう。外観のアクセントとしてFIX窓(はめ殺し窓)を効果的に使うなど、やり方はいくらでもあります。無駄な窓を減らすことは、建築費を抑え、高性能で美しい家を建てるための第一歩です。
4.シャッターは「安心感」という名の高価な気休め?
「台風や防犯のためにシャッターは必須ですよね?」これも、施主から当たり前のように出てくる要望の一つです。しかし、これも営業マンが積極的には勧めないオプションです。特に、1階の掃き出し窓以外への設置は、オーバースペックと判断されることが多いでしょう。
なぜ勧めないのか?
防犯性能は「ガラス」で確保する時代:ひと昔前は「シャッター=防犯」でしたが、現在は「防犯ガラス(CPマーク付きガラス)」が主流です。ガラス自体が破られにくいため、シャッターがなくても警察が駆けつけるまでの時間を十分に稼げます。シャッターをこじ開ける音や時間よりも、ガラスを破る方が侵入犯にとってはリスクが高いのです。
台風対策としても過信は禁物:確かに飛来物からガラスを守る効果はありますが、近年のスーパー台風ではシャッターごと破損したり、シャッターの隙間から浸水したりするケースも報告されています。そもそも、現在の住宅用窓ガラスは非常に強度が高く、簡単には割れません。
開閉の手間と「開かずのシャッター」化:電動シャッターは高価ですし、手動シャッターは毎日の開け閉めが非常に面倒です。結果的に、ほとんど開け閉めしない「開かずのシャッター」になっているお宅は驚くほど多いのが実情です。使わない設備に何十万円もかけるのは、賢い選択とは言えません。
メンテナンスの問題:シャッターボックスに鳥や蜂が巣を作ったり、故障したりと、意外と維持管理に手間や費用がかかることもあります。
代替案と考え方
防犯が目的なら、迷わず「防犯ガラス」や「防犯フィルム」を採用しましょう。コストを抑えつつ、シャッター以上の効果と日々の利便性を得られます。どうしても不安な大きな窓(掃き出し窓など)にだけシャッターを設置し、他の窓は防犯ガラスにする、というハイブリッドな考え方が現実的です.
「シャッターがある」という物理的な安心感は確かにあるかもしれません。しかし、その安心感のために支払うコストと、日々の手間、将来のメンテナンス費用が見合っているかを冷静に判断することが重要です。
5.全館空調は「諸刃の剣」、覚悟が必要な超高級オプション
家中の温度を一定に保ち、どこにいても快適。ヒートショックの心配もない。そんな夢のような「全館空調」ですが、営業マンがこれを安易に勧めることはまずありません。むしろ、お客様から強い要望がない限り、話題にすら出さないケースも多いでしょう。
なぜ勧めないのか?
莫大な初期費用と交換費用:全館空調の導入コストは、一般的な壁掛けエアコンに比べて圧倒的に高額で、150万〜300万円以上かかることもザラです。さらに恐ろしいのが、15年〜20年後のシステム全体の交換費用です。その時にも、同等かそれ以上の費用がかかることを覚悟しなければなりません。
故障時のリスクが甚大:システムが一つであるため、万が一故障した場合、家全体の冷暖房がストップしてしまいます。真夏や真冬に故障したら…と考えると、そのリスクの大きさが分かるはずです。修理も特殊な技術が必要で、高額かつ時間がかかる可能性があります。
家族間の「体感温度」の違いに対応しにくい:「お父さんは暑がりだけど、お母さんは寒がり」といったご家庭は多いもの。全館空調は部屋ごとの微細な温度調整が苦手なモデルも多く、家族全員が快適に過ごすのが意外と難しいという声も聞かれます。子どもが小さいうちは部屋も使わないためその場合はまるまる無駄になってしまいます。
ランニングコストの問題:24時間つけっぱなしが基本のため、家の断熱性能が中途半端だと、電気代がとんでもない金額になる恐れがあります。つけるにしても、太陽光発電や蓄電池でランニングコストを抑えられるようにはしておきたいところです。
代替案と考え方
現代の家づくりにおける最適解は、「家の高気密・高断熱化+高性能な個別エアコン」です。
魔法瓶のように家の性能を高めておけば、夏は小屋裏(屋根裏)に設置したエアコン1台、冬は床下に設置したエアコン1台で、家全体の温度を快適に保つことが可能です。この方法なら、初期費用もランニングコストも全館空調よりはるかに安く、故障時のリスクも分散できます。
全館空調は、経済的にかなりの余裕があり、将来の交換費用も受け入れられるという覚悟を持った上で採用すべき、いわば「王様のオプション」です。その快適性は確かに素晴らしいものですが、ほとんどのご家庭にとっては、家の性能そのものにお金をかける方が、はるかに賢明で持続可能な選択と言えるでしょう。
まとめ:オプション選びは「思考停止」しないことが何より重要
今回ご紹介した5つのオプションは、決して「付けてはいけない」ものではありません。あなたのライフスタイルや価値観、そして予算によっては、最高の選択肢になる可能性も十分にあります。
大切なのは、「みんな付けているから」「便利そうだから」といった理由で安易に採用を決めてしまう「思考停止」を避けることです。
- そのオプションで、本当にあなたの暮らしは豊かになるのか?
- そのために支払うコスト(初期費用+ランニングコスト)に見合っているか?
- もっとシンプルで、コストパフォーマンスの良い代替案はないか?
住宅営業マンは、あなたの家づくりのパートナーですが、時には「標準仕様でスムーズに契約したい」「クレームにつながりそうなオプションは避けたい」という本音も持っています。彼らの提案を参考にしつつも、最後はあなた自身の頭で考え、納得して決断することが、後悔のない家づくりの最大の秘訣です。
ぜひ、今回の記事を参考に、あなたとご家族にとって本当に必要なものを見極め、最高のマイホームを完成させてください。
暮らしのセカンドオピニオンでは、家づくりの相談をお受けして、その方にあったハウスメーカーや工務店を紹介することも可能です。「見れば見るほど分からなくなる」のが家づくり。さまざまな経験から忖度なしでお話が出来ますのでご興味ある方は一度無料相談にお申し込みください。