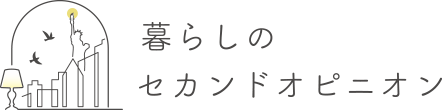【106万円の壁・撤廃確定】「手取りが減るだけ」は嘘?本当? 年金の損得計算から見えた、私たちがすべきこと
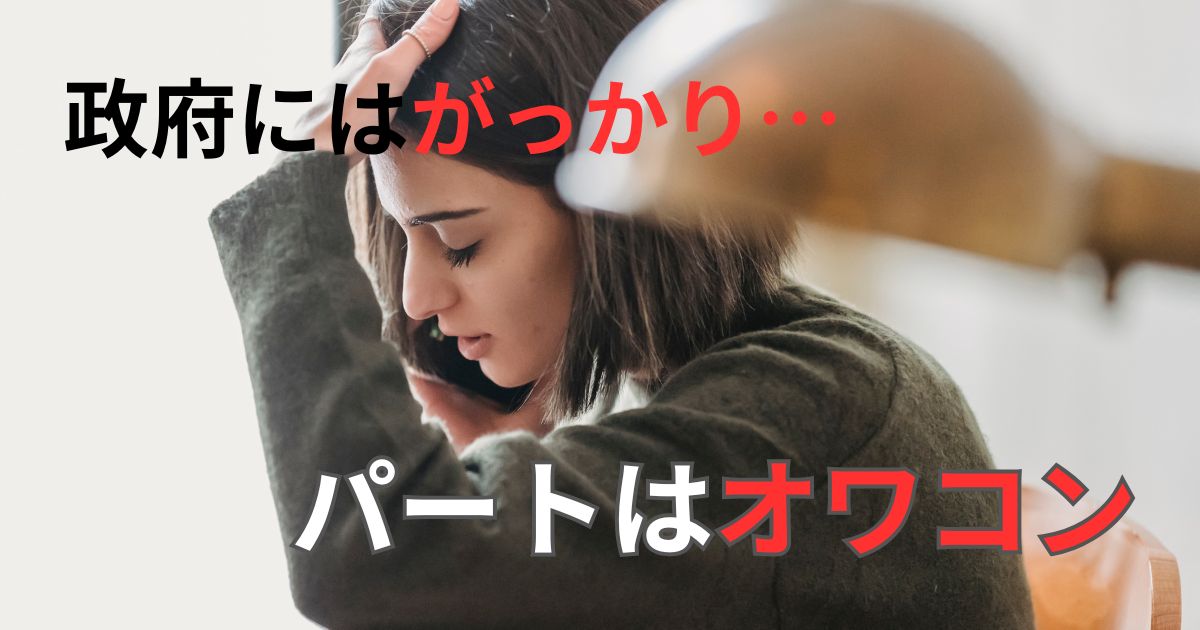
「また手取りが減る話か…」 「結局、国はもっと保険料を取りたいだけでしょ?」
2025年6月、社会保険の「106万円の壁」を撤廃する年金制度改革法が成立したというニュースに、そんなため息をついた方も多いのではないでしょうか。
これは「いつかそうなるかも」という曖昧な話ではなく、私たちの働き方と家計に直結する「確定した未来」です。
巷では「損だ」「改悪だ」という声が溢れていますが、その一方で「チャンスだ」という意見もあります。
一体、何が真実なのでしょうか?
この記事では、単なる制度解説に留まらず、多くの人が最も気になる「リアルな損得勘定」から、見過ごされがちな「本当のメリット」、そしてこの変化を乗りこなし未来を切り拓くための具体的なアクションまで、徹底的に掘り下げていきます。
まずは確定情報を再確認:何が、どう変わるのか?
今回の法改正で焦点となったのは、パート・アルバイトの社会保険加入基準です。これまでは勤務先の企業規模によって基準が異なりましたが、今後は以下のように変更されます。
【社会保険の加入基準】
- これまで:
- 従業員51人以上の企業 → 年収106万円以上で加入
- 従業員50人以下の企業 → 年収130万円以上で加入
- これから:
- 従業員51人以上の企業 → 年収要件を撤廃
- 従業員50人以下の企業 → 変更なし(130万円の壁は存続)
つまり、比較的人数の多い企業で働く場合、「年収」という基準そのものがなくなります。 代わりに、以下の条件を満たせば、原則として社会保険への加入が必須となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間の見込みが2ヶ月以上
- 学生ではない
今後の大きな判断基準は「年収」から「週20時間以上働くかどうか」にシフトすると覚えておきましょう。
【本音】最大の懸念。「手取り減」と年金の不都合な真実
「結局、強制的に保険料が引かれて手取りが減るんでしょ?」
この懸念は、まさしくその通りです。そして、多くの人が「改悪だ」と感じる最大の理由がここにあります。
SNSでは「国民から搾り取る気か!」「これ以上、負担を増やすな!」といった怒りの声が沸いています。この感情は、単なるイメージではありません。冷静に損得を計算してみると、その「コスパの悪さ」が分かります。
【衝撃シミュレーション】保険料の元を取れるのは93歳!?
仮に、現在40歳、年収106万円の方が新たに社会保険に加入したケースで計算してみましょう。
- 毎月の保険料負担: 約12,500円(年間 約15万円)
- 20年間加入した場合の総支払額: 約300万円
これに対し、将来受け取れる年金(老齢厚生年金)はいくら増えるのでしょうか。
- 将来増える年金額: 月々 約9,000円
20年間で300万円を支払っても、年金の上乗せ額は月1万円にも満たないのです。 支払った保険料の元を取るには、65歳で受給を開始してから約28年かかります。つまり、93歳になってようやくプラスに転じる、という計算になります。
日本人の平均寿命(男性約81歳、女性約87歳)を考えれば、「これでは割に合わない」「払いたくない」と感じるのも無理はありません。この損得勘定だけを見れば、今回の制度変更が歓迎されない理由は明らかです。
【逆転の発想】それでも「得」と言える、社会保険の2つの本質的価値
では、私たちはこの「コスパの悪い」制度変更を、ただ嘆くしかないのでしょうか?
目先の損得勘定だけでは見えない、社会保険が持つ2つの本質的な価値に目を向けると、全く違う景色が見えてきます。
価値1:月々の保険料では買えない「最強のセーフティネット」
社会保険の最大の価値は、将来の年金よりも、むしろ「現役時代の万が一の保障」にあります。
例えば、扶養内で月8万円稼ぐAさんと、社保に加入して月10万円稼ぐBさん。手取り額はほぼ同じですが、2人の「安心感」は天と地ほどの差があります。
Bさんが加入する会社の健康保険には、国民健康保険にはない、強力なセーフティネットが備わっているからです。
- 傷病手当金: 病気やケガで4日以上働けなくなった時、給与の約3分の2が最長1年6ヶ月支給される。
- 出産手当金: 出産で会社を休んだ時、給与の約3分の2が支給される。
- 障害厚生年金: 障害を負った場合、国民年金に上乗せして年金が支給される。
人生、何が起こるかわかりません。突然の病や事故で働けなくなった時、収入が途絶える不安から守ってくれるこれらの保障は、月々数万円の保険料では決して買えない、非常に価値のある「保険」なのです。
価値2:「働き控え」という“機会損失”からの脱却
「保険料を払いたくないから、働く時間をセーブする」
この「働き控え」という思考こそ、実は最大の“機会損失”かもしれません。
次のどちらの家計が豊かになるか、考えてみてください。
- ケースA: 壁を意識して年収100万円に調整。税・社保負担は0円で、手元に100万円残る。
- ケースB: 壁を気にせず年収200万円稼ぐ。税・社保で約40万円引かれても、手元に160万円残る。
答えは明白です。 目先の負担を避けるために、本来得られるはずだった数十万円の収入と、それに伴うキャリアアップの機会を失うのは、非常にもったいない選択です。
壁の撤廃は、私たちをこの「もったいない」状況から解放し、「手取りの絶対額を最大化する」という、より本質的な目標へと向かわせるきっかけになり得ます。
【未来設計】壁なき時代、私たちはどう働き、どう備えるか
制度変更は避けられない事実です。重要なのは、この変化をどう捉え、どう行動するかです。
これからの時代を生き抜くために、私たち個人ができることを3つのステップで考えてみましょう。
- 価値観をアップデートする:「時間給」から「生涯価値」へ。 目先の「手取り額」だけで損得を判断するのをやめましょう。将来の年金、万が一の保障、そして労働時間を増やすことで得られるスキルや経験といった「生涯にわたって得られるトータルの価値」で働き方を判断する視点が必要です。
- 「稼ぐ力」を本気で強化する:社会保険料の負担増を乗り越え、豊かさを実現するには、収入の絶対額を増やすしかありません。単に労働時間を増やすだけでなく、資格取得やスキルアップに投資し、より付加価値の高い仕事(=時間単価の高い仕事)を目指しましょう。
- 「増やす力」を身につける:増税、物価高、そして社会保険料の負担増。給料だけで資産を築くのが難しい時代だからこそ、稼いだお金の一部を未来のために働かせる「資産形成(投資)」の視点が不可欠です。NISAなどを活用し、少額からでも「お金に働いてもらう」経験を始めましょう。
まとめ:変化を「機会」に変え、主体的に未来を創る
「106万円の壁」の撤廃は、短期的には手取りが減るという痛みを伴います。目先の利益だけ見れば、不満を感じるのも当然です。
しかし、この変化を「搾取だ」と嘆いて思考停止するのではなく、「働き方を根本から見直し、キャリアと資産を主体的に築く絶好の機会だ」と捉え直すことはできないでしょうか。
壁がなくなることで、私たちはもっと自由に、自分の可能性を最大限に発揮できるフィールドに立つことができます。
極端な話、「壁なんて気にせず、バリバリ稼いでしまおう!」という話です。
手厚い保障という安心の土台の上で、思い切り「稼ぐ力」を発揮し、賢く「増やす力」を身につける。この変化を前向きなエネルギーに変え、5年後、10年後に笑っていられる未来を、自らの手で創り上げていきましょう。